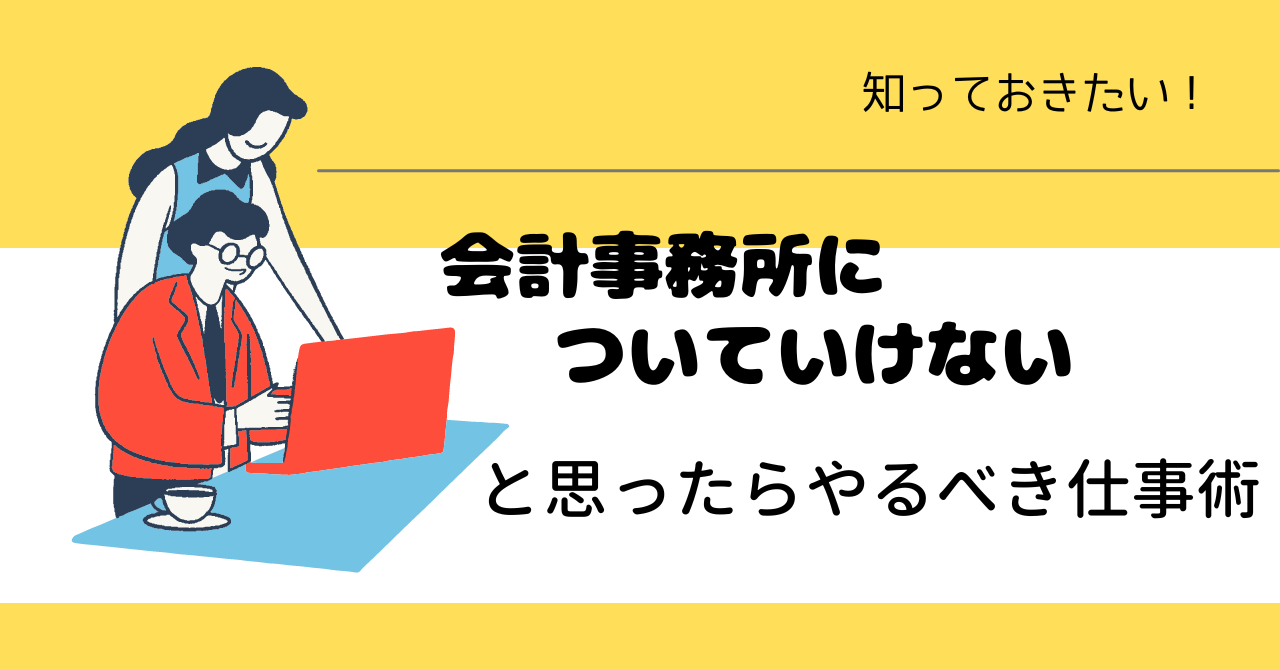会計事務所に就職したものの…
わからないことが多すぎて、仕事についていけない。
能力不足でしょうか?
会計事務所に就職してみたものの…仕事が思うようにできなくて「ついていけない」「能力不足かな?」と落ち込むことはありませんか?
・未経験なのにすぐに担当を持たされた
・先輩が仕事を教えてくれない
・お客さんと上手にコミュニケーションがとれない
税理士法人や会計事務所は教育体制が整っていないことが多く『仕事をしながら学べ』のスタイルが主流です。
何もわからないところからお客さんの前に放り出されて、つらい日々を過ごしている未経験の方も少なくないでしょう。
私自身も新人1年目は体当たりで仕事を覚える一番つらい時期でした。
そこで今回は、新卒から税理士事務所に5年以上勤務している管理人が、昔の自分に教えたい「会計事務所についていけない」と悩んだらやるべき仕事術についてお話しします。
転職という選択肢を検討する際のポイントについてもお話ししますので、ぜひお付き合いください。
- 簿財法+院免の30代勤務税理士
- 新卒入社で常時残業があるブラック税理士法人で働くも、4年目に転職を決意
- 次は絶対ホワイトに転職したくて、業界専門の転職エージェント5社以上に登録
- キャリア面談で自分を見つめ直し、超自由なフルリモート税理士法人へ転職成功!!
- 通勤なし、往訪なし、飲み会なしで、プライベート時間が爆増
- 『働く場所で人生は変わる』と実感中
筆者イチオシ!会計事務所向け転職エージェント


ブラックNGの厳選求人
「ホワイトな税理士事務所のみしか紹介しない」と公言するほどの、定着率にこだわった無料の転職支援サービス
厳選された離職率3%レベルの求人から選べるから、ブラック事務所遭遇の確率をグンと減らせる
ホワイトな事務所で長く働きたい人は、マストで登録すべき新時代のエージェント



「給料や休日が不当ではないか?」「残業が多すぎないか?」「早期退職者ばかり出ていないか?」などの一定の基準を設け、厳格な審査を通過したホワイトな求人のみ保有・紹介してくれます。
厳選ゆえに保有求人が少ないことがネックですが、ブラック事務所への転職ミスをしないために、登録必須なエージェントです。
詳細なミツプロの評価記事はこちらへ
【新人はつらい】会計事務所の仕事についていけない理由


会計事務所は仕事を教えてくれない
会計事務所は一般企業のようなOJT制度(先輩社員が後輩に対し、業務に必要な知識やスキルを、実務を通して指導・教育する制度)が整っていないことが多いです。
理由は複数あるかと思いますが、基本的に自分の仕事で手一杯のことが多く、新人の面倒を見ている暇がありません。
また、それぞれが「わからないことは自分で調べて解決する」ことで仕事を覚えてきているため、同じように新人も体当たりで学んでいくだろうという風潮があります。
・仕事を教える時間的余裕がない
・短期で辞める社員も多く教育コストがかけられない
・「自力で仕事を覚えた」自負があるため同じように成長できると考えている
中堅以上の税理士法人では新人研修を行うところもありますが、結局研修と実務では異なるため「自ら学んで仕事を覚える」覚悟が必要な業種となります。
未経験でも担当を持たされる
会計事務所は現在業界的に圧倒的「人手不足」です。
AIの発達により税理士業務がなくなるという話もありますが、人の手が要らないレベルには到底達していない現状です。
むしろ税理士試験受験者は年々減少しており、税理士の平均年齢は60歳以上と若い人材が枯渇している状況です。
そのため、未経験で入社しても、人手が足りていないためすぐに担当を持たされることが多いです。
私も新卒入社と同時に退職予定者から10社以上の引継ぎを受けました。
会計事務所は一人担当制が多いため、引継ぎを受けた時点から、お客さんはあなただけが頼りなのです。
質問される範囲が広すぎる
税理士業務は多岐に渡ります。
税務の質問一つでも「法人税法」「消費税法」「所得税法」…と様々な税務論点を総合的に検討する必要があります。
税務だけならまだしも、「給与計算」や「社会保険・雇用保険」、「補助金・助成金」、「融資」…と会社経営に関することであれば何でも質問されるような職業です。
経営者を総合的に支援できることがこの仕事の醍醐味なので、日々の勉強が不可欠です。
お客さんとのコミュニケーションが上手くいかない
「会計事務所は事務作業」と考えて入社された方は、想像以上にコミュニケーション能力を求められて驚かれるのではないでしょうか。
会社へ訪問して経営者や経理の人へアドバイスをするのも会計事務所の重要な仕事の一つです。
税務の話だけではなく、経営や人事の相談、ビジネスの話、雑談まで振られる話は幅広いです。
また、決算のタイミングでは資料を期限内に回収するという重要任務があります。
資料の依頼・回収方法、期日設定、リマインド等、お客さんに動いてもらうにはどうしたら良いか考え、伝え方を工夫することも大切です。
税理士(会計事務所)は、お客さんと良好な関係を保って期限内に仕事をするために、幅広い知識とコミュニケーション能力が要求される難しい職業だと思います。
会計事務所で活躍するには「自ら学ぶ姿勢」が必要
会計事務所で活躍するためには「自ら学ぶ姿勢」がとても大切です。
上記の通り、教育体制が整っていない業界かつ、幅広い知識のアップデートが常に必要な仕事だからです。
とはいえ、未経験者はどのように仕事を覚えていけば良いのかわからない人も多いと思います。
私も1年目は仕事の進め方がわからずとても大変な思いをしました。
そこで「会計事務所の仕事についていけない」と苦しんだ過去の自分に伝えたい仕事のコツについてお話したいと思います。
自分の能力不足ではないかと悩んでいる方は、ぜひ次の仕事術を明日から試してみてください。
調べるスキルを身につける


会計事務所で仕事をする上で最も重要なのは「調べるスキル」です。
わからないことが発生したら、まずは「自分で調べて、自分なりの回答を準備する」ことをマストで行ってください。
先輩社員に質問するのはその後です。
調べものをする時は、以下の手順で行いましょう。
① 過去の記録を調べる
② Web検索で当たりを付ける
③ 国税相談専用ダイヤルに電話をかける
④ 条文、書籍、税務通信で根拠を探す
① 過去の記録を調べる
もし引き継いだ会社からの質問であれば、まずは前期以前の会計処理、税務処理を確認しましょう。
処理方法が確認できたら「なぜ前任者はその処理をしたのか」を考えます。
「前の担当者がこうしていたから」で済ませてしまうのはNGです。
前の担当者が間違っている可能性もありますし、他の会社で同様の事例が出た際に、自信を持って同じ判断をすることができないからです。
きちんと過去の処理が腹落ちできるように、面倒ではありますが、調べる習慣をつけましょう。
② Web検索で当たりを付ける
会計事務所の社員たるもの、最終的には条文に立ち返って判断するようにしたいですが、初めから条文を探しにいく様ではいつまでたっても回答には近づけません。
今はインターネットで様々な税理士が己の見解を発信してくれている時代です。
わからないことは一度Web検索をし、複数サイトを比較・閲覧した上で、正解の当たり(方向性)をつけましょう。
もちろん、ネット情報は信憑性を確保してくれるものではありません。
ただ、複数サイトで同じ見解を発信しているようでしたら、正解にかなり近いと判断できると思います。
ネット情報を根拠とするのではなく「問題解決の糸口となる情報を早く見つける」ためにうまく活用すると良いでしょう。
③ 国税相談専用ダイヤルに電話をかける
国税に関する一般的な相談については、国税庁が「国税相談専用ダイヤル」を用意してくれています。
国税局の職員等が電話相談を受けてくれるため、こちらも上手く活用していきましょう。
電話をかける際の注意点は「会計事務所の社員」と名乗らないことです。
会計事務所からと悟られると「税理士先生にてご判断をお願いします」と断られてしまう可能性があるからです。
事業主や会社経理を装って(難しい言葉は使わず知識がないフリをして)質問するように意識してみてください。
④ 条文、書籍、税務通信で根拠を探す
①~③までを活用すれば、ほぼ正解までたどり着けているはずです。
ただ根拠はきちんと残しておくべきです。
判断のもととなる条文や書籍はPDF化して、仮に税務調査で指摘された際に、反論できるよう準備しておきましょう。
「税務通信」を購読している事務所であれば、税務通信の記事も勉強になるので、調べてみることをおすすめします。
質問するスキルを身につける


「調べるスキル」が身についたら、次は「質問するスキル」です。
質問する相手は、大きく2つ「社内(先輩や上司)に対する質問」と「お客さんに対する質問」かと思います。
どちらに対する質問でも意識してほしいのが下記の事項です。
① 質問の前提を共有する
② 自分なりの答えを用意する
③ 答えを記録する
① 質問の前提を共有する
新人の方でまず多いのは、「質問の前提を共有せずに質問を始めてしまう」ことです。
社内への質問でしたら、「クライアント名」や「クライアント状況」「なぜこの質問をしたいのか」は冒頭で説明してから、質問に入ると良いでしょう。
お客さんへの質問の場合でも、「現状について○○という認識でおります」と自分が認識している状況を先に共有すると、仮に現状に相違があった場合に、早い段階ですり合わせをすることができるので、おすすめです。
税理士業務は、ケースバイケースで答えが変わることが多い仕事です。
前提が間違っていると、異なる答えになってしまう可能性がありますので、「質問の前提を共有する」ことを意識するようにしてみてください。
② 自分なりの答えを用意する
既にあなたは「調べるスキル」を駆使して、自分なりの答えを用意できているはずです。
「質問の前提の共有」と共に、「今回のケースの場合、この条文(書籍)からこのような解釈ができると思うのですが、あっているでしょうか?」と自分の答えと答えに達するまでの過程を説明するようにしましょう。
厳しいですが、自分の答えを用意せずに「これってどうすればいいですか?」と丸投げするようでは、自分で考える力が身につきませんし、先輩からも呆れられてしまうと思います。
正解にたどり着けていなくてもいいのです。
あなたの答えとそれまでの過程を説明してくれれば、多くの先輩はどこで考え方が間違ってしまったのか教えてくれると思います。
質問を丸投げして答えだけ貰うより、答えの導き方を教えて貰う方が何倍も有意義です。
「魚を与えるより釣り方を教える」
せっかくなら魚の釣り方(答えの導き方)を身につけていきましょう。
あと先輩の立場からしてみても、自分なりに考えてから質問を持ってきてくれる後輩の方が、やっぱり可愛くみえるものです。
③ 答えを記録する
これも意外と多いのですが、「解決した答えを記録しない」のはとてももったいないことです。
質問時には記憶に新しいので、質問から答えまでの過程を覚えていると思いますが、人間ですから時間が経つと忘れてしまいます。
忘れてしまうとせっかく時間をかけて答えまで導き出したのに、もう一度同じように考え直す必要があり、とてももったいないと思いませんか?
解決した事項は、早めに「質問」「質問の前提」「答え」「答えまでの過程」をワンセットにして、記録するようにしましょう。
自分が次の人へ業務の引継ぎをするときも、その記録があれば、スムーズな引継ぎが可能です。
回答するスキルを身につける


最後にお伝えしたい仕事スキルは「回答するスキル」です。
これは少し応用編なので、まずは「調べるスキル」と「質問するスキル」を身につけて余裕があるようでしたら、意識してみてください。
① 質問意図を読み取る
お客さんからの質問、社内質問のどちらにも共通しますが、質問をされたら「質問意図」を読み取ることをまず意識するようにしましょう。
この場合の質問意図とは、「なぜこの質問をしているのか」「相手が望んでいる答えは何か」を想像することです。
例えば「○○は経費になりますか?」という質問に対して、「なぜこの質問をしているのか」「相手が望んでいる答えは何か」を想像すると、以下の可能性が考えられます。
■ なぜこの質問をしているのか?
① きちんとした経理処理をしたいから
② 節税のために多少強引でも経費に落としたいから
■ 相手が望んでいる答えは何か?
① 基本的に○○は経費になりません。理由は~だからです。
② 基本的に○○は経費になりませんが、△△の場合なら経費と認められる可能性はあります。
このように、相手の質問意図がどこにあるのかによって、回答の仕方が少し変わります。
質問意図を読み取れない場合でも、追加の質問で確認されるだけですので、できなくても仕事に大きな影響はありません。
ただ、質問意図を踏まえて回答することで、連絡やり取りを少なくすることができ、お互いにストレスが少なく済むので、仕事に慣れてきたらぜひ考えるようにしてみてください。
② プラスαの回答を意識する
質問意図を考えられるようになったら、その意図に沿った「プラスα」の回答を心掛けましょう。
先ほどの「○○は経費になりますか?」の質問の場合だと以下のイメージです。
■ なぜこの質問をしているのか?
・ 節税のために多少強引でも経費に落としたいから
■ 相手が望んでいる答えは何か?
・ 基本的に○○は経費になりませんが、△△の場合なら経費と認められる可能性はあります。
■プラスαの答え
・ 調査の際に否認されるリスクはありますが、もし経費として計上する場合には、□□の証拠を残しておくとよいかと考えております。
完全に経費として認められないような内容でしたら、それは専門家としてきちんと指摘するべきですが、ケースバイケースで認められる余地があれば、そこはアドバイスをするべきだと私は考えています。
その際に、質問に対するプラスαとして「こうすれば認められる可能性がある」といった、質問の先の回答まで準備できるようになると、会計事務所で立派に活躍することができるでしょう。
能力不足ではなく『やり方』がわからないだけ


「自分が会計事務所についていけないのは、能力不足だからではないか…?」と悩んでいるあなたはとても真面目で責任感のある方です。
会計事務所の仕事内容は、1年をスパンとしたルーティン業務が多いため、まずは1年間回してみてください。
1年後には、慣れて余裕が出てきます。
能力不足ではなく、まだ『やり方』がわかっていないだけです。
会計事務所の閉鎖的な環境に負けず、もう少し一緒に頑張りましょう!
【厳選2冊】会計事務所の未経験者におすすめの本
ここまで会計事務所で活躍するための仕事術についてお話してきましたが、書籍によるインプットをすることで成長速度はさらに加速します。
下記2冊は、実際に管理人が読んで、会計事務所の未経験者に最もおすすめの本なので、ぜひ読んでみて欲しいです。
◆ 税理士事務所に入って3年以内に読む本(高山弥生)
レビュー記事:【未経験者必読】税理士事務所に入って3年以内に読む本
◆ STEP式 法人税申告書の作成手順
※最新版の購入をお願いします
レビュー記事:【申告書作成初心者おすすめ】STEP式 法人税/消費税/相続税申告書の作成手順
まとめ
未経験で会計事務所へ入社すると、新人のうちは、わからないことばかりでつらいと思います。
ただ経験を積めば積むほど、仕事のやりがいを感じることができるはずので、ぜひ今回の仕事術を意識して日々の業務に取り組んでみてください。
調べ方や質問の仕方を少し意識するだけで、成長速度がかなり違うはずです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。



会計事務所は慣れるまでが一番大変です!今は辛抱の時!!
最後に、「ついていけない自分が悪い」と感じているあなたへ。
業務は属人的、説明は雑、教育はほぼ放置。
それでも「できない自分が悪い」「仕事が遅いのは甘え」──
そんな空気に、飲み込まれていませんか?
誰もがはじめは仕事なんてできないものです。
あなたの本当の実力ではありません。
今の会計事務所に“人を育てる仕組み”がないだけ。
世の中には、
・未経験や若手をちゃんと育てる気のある事務所
・質問が歓迎される雰囲気のある職場
・努力が正当に評価される環境
…が、ちゃんと存在します。
それを知らずに、「自分はダメだ」と思い続けるのは、本当にもったいない。
転職=逃げではありません。
見限るべきものを、正しく見限る力です。
信頼できるエージェント3社(完全無料)をまとめたので、よければ見てみてください。